2025/04/07 20:35
情報・通信
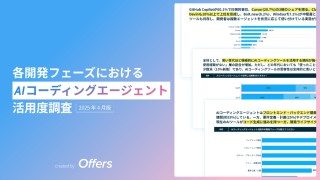
エンジニア、PM、デザイナーのキャリアインフラ「Offers(オファーズ)」を運営する株式会社overflow(本社:東京都港区、代表取締役:鈴木裕斗・田中慎、以下 overflow)は、Offersサービス会員に対して、サービス内でアンケートを実施し、「各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度」を調査しましたのでその結果をお知らせします。
■「【2025年4月 版】各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度調査」のダウンロードはこちら
https://offers.jp/worker/wp/ai-coding-agent-survey-202504
■ 本調査結果データの引用について
本調査結果データを一部引用・二次利用等される場合は、「【2025年4月 版】各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度調査|Offers」と表記の上、リンクのご協力をお願いいたします。
リンク先: https://offers.jp/worker/wp/ai-coding-agent-survey-202504
【調査概要】
<調査目的>
各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度調査
<調査方法>
Offersサービス会員に対して、サービス内でアンケートを実施
<調査期間>
2025年3月 上旬
<調査対象>
Offers会員ユーザー
<回答者数>
208名
※1|合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。
【調査目的とその背景】
2025年は「AIエージェントの年」と言われ、特にエンジニア界隈ではコーディングに特化したAIエージェントが大きな注目を集めています。しかし日本においては、海外と比較してジェネレーティブAIの活用率が依然として低く、企業での本格導入には信頼性・コスト・セキュリティ・企業文化など多くの障壁が存在していることが指摘されています。
「Offers」ではこれまで、プロダクト開発に関わる人材のマッチングを提供してまいりました。サービスを提供する中で、開発現場におけるAIツールの活用状況やその影響に関する情報が不足していることに気づき、より良いキャリア支援を行うためにも実態調査の必要性を感じました。
本調査では、現場で実際に活用されているAIツールや各開発フェーズごとの使い分け、導入メリットと課題を体系的に整理することで、「AIを使いこなす開発者」が活躍できる環境を整備するための貴重なデータを提供します。Offersとしては、急速に進化するAI技術の波に取り残されることなく、エンジニアの皆様に最適な支援を提供するため、現場の生の声を反映した情報発信を目指しています。
【調査結果】
<サマリコメント>
・AIコーディングエージェントは「日常的に使用」41.8%と「時々使用」21.6%で計63.4%が実際に活用中。
・GitHub Copilotが60.1%で圧倒的首位、Cursor(20.7%)の3倍のシェアを誇る。Claude Code(15.4%)、v0(14.9%)、Devinも10%以上で上位を形成し、Bolt.new(8.2%)、Windsurf(7.2%)が中堅層として続く。一強市場ながら特化型ツールも共存し、開発者は複数エージェントを状況に応じて使い分けている実態が見られる。
・AIコーディングエージェントの利用頻度は年代によって異なり、20〜40代は約6割が毎日または週に数回利用しているが、50代以上では利用頻度が低下し、未利用者(25.9%)も増加。
・AIコーディングエージェントはフロントエンド・バックエンド開発で最も活用され(50%以上)、デザイン・テスト分野も健闘(約33%)している。一方、要件定義・計画(25%)やデプロイメント・運用(10%未満)での採用は限定的。この傾向から、現在のAIツールがコード生成に強みを持つ一方、開発ライフサイクルの両端ではまだ発展の余地が大きいことがわかる。
・AIコーディングエージェント利用において「特にルールなし」が33%と最多であり、企業・個人双方での適切なガイドライン整備が今後の課題である。
<AIコーディングエージェント利用状況サマリ>
GitHub Copilotが60.1%で圧倒的首位、Cursor(20.7%)の3倍のシェアを誇る。Claude Code(15.4%)、v0(14.9%)、Devinも10%以上で上位を形成し、Bolt.new(8.2%)、Windsurf(7.2%)が中堅層として続く。一強市場ながら特化型ツールも共存し、開発者は複数エージェントを状況に応じて使い分けている実態が見られる。
<AIコーディングエージェントの利用経験の有無(年代別)>
全体として、若い世代ほど積極的にAIコーディングツールを活用する傾向が強く、年代が上がるにつれて「興味はあるが使用経験がない」層の割合が増加。ただし、どの年代においても「使ったことがないし、導入予定もない」という回答は少数派(10%前後)であり、AIコーディングツールの受容性は全体的に高いと言える。
<AIコーディングエージェントの利用経験の有無(経験年数別)>
経験年数3〜5年の開発者がAIコーディングを最も積極的に活用。日常的使用は全経験層で約40%と安定している一方、経験1〜3年の層には消極派が多く、5年以上のベテラン層では「使ったことがないが興味はある」が目立つ。
<AIコーディングエージェントの利用頻度(年代別)>
AIコーディングエージェントの利用頻度は年代によって異なり、20〜40代は約6割が毎日または週に数回利用しているが、50代以上では利用頻度が低下し、未利用者(25.9%)も増加。全体的に頻繁に使うグループと全く使わないグループの二極化が見られる。
<AIコーディングエージェントの利用頻度(経験年数別)>
経験3〜5年の開発者がAIコーディングツールを最も積極的に活用しており、約69%が週1回以上利用。「毎日」使用は全経験層で約35%と共通だが、経験1〜3年層では非利用者が30%と多く、5年以上層でも非利用者が約20%存在する。
<AIコーディングエージェント利用時のルール/ガイドラインについて>
AIコーディングエージェントの利用ルールは「特に定めていない」33.7%と「個人の自己ルール」29.3%で計63%が非公式な状態。一方、「企業ポリシーによる制限」26.4%を筆頭に約34%が組織的ルールに従い、「著作権規定」も1.9%ある。現状は個人判断が主流だが、情報保護の観点から公式ガイドラインへの移行が進みつつある様子がうかがえる。
<AIコーディングエージェントの利用歴について>
AIコーディングエージェントの利用歴は短く、3か月以内の新規ユーザーが31.3%と最多で、半年以内では半数近く(49.6%)を占める。1年以内の利用者は全体の71.7%に達し、2年以上のベテランはわずか7.7%にすぎない。この分布からは、AIコーディング支援ツールの普及が最近になって急速に進んでいることが読み取れる。
<AIコーディングエージェントの利用満足度>
AIコーディングエージェントへの満足度は高く、「満足」以上が59.3%で、特に「満足」が41.1%と最多。「どちらともいえない」も37.0%と多いが、否定的評価はわずか3.7%にとどまる。これはAIツールが広く受け入れられている一方、活用法の確立によってさらなる満足度向上の余地があることを表している。
<AIコーディングエージェントを利用している開発フェーズ>
AIコーディングエージェントはフロントエンド・バックエンド開発で最も活用され(50%以上)、デザイン・テスト分野も健闘(約33%)している。一方、要件定義・計画(25%)やデプロイメント・運用(10%未満)での採用は限定的。この傾向から、現在のAIツールがコード生成に強みを持つ一方、開発ライフサイクルの両端ではまだ発展の余地が大きいことがわかる。
【直近開催予定のイベントご案内 #Offers_DeepDive】
① 多要素認証じゃダメ?ritouさん、Auth屋さんに聞く 認証技術の最前線 ~パスワードレスとは~
<イベントでわかること>
・パスワードレス認証とは?
・各認証技術(パスワード認証、二段階認証・多要素認証、パスワードレス認証)の成り立ち
・認証技術を検討する際の技術選定のポイント
<開催概要>
・【開催形式】オンライン開催
・【日時】2025年4月17日(木) 19:00~20:00
■本イベント参加申し込み・詳細はこちら
https://offers.jp/worker/events/connpass_56
② そのID管理、サービス増えても大丈夫? LayerX/kubellに聞く 後から後悔しないID基盤設計
<イベントでわかること>
・実際のマルチプロダクト移行事例、直面した課題
・マルチプロダクトを考えるにあたり意識すべきID管理設計
・IDaaSとの向き合い方
<開催概要>
・【開催形式】オンライン開催
・【日時】2025年4月23日(水) 19:00~20:00
■本イベント参加申し込み・詳細はこちら
https://offers.jp/worker/events/connpass_57
Offersでは、本調査以外にも最新の技術トレンドやエンジニアのキャリアに関する様々な情報を発信しています。ぜひご覧ください。見逃し無料配信!続々追加中!
︎過去の人気イベントのアーカイブ配信はこちら
https://offers.jp/worker/events
■ 「Offers(オファーズ)」とは
「Offers」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月 に正式リリースし、2024年4月 時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。
● Offersに関する情報はこちら
・「働くを楽しく」するマガジン「Offers Magazine」: https://offers.jp/media
・開発組織におけるHR担当者やマネージャーのための情報メディア「Offers HR Magazine」: https://hr-media.offers.jp/
・副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」: https://offers.jp/jobs
・プロダクト開発の知見が集まるQ&Aプラットフォーム「Offers Q&A」: https://offers.jp/qa
・デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」: https://hr-lab.offers.jp/
■ 「Offers MGR(オファーズマネージャー)」とは
「Offers MGR」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、エンジニア、PM、デザイナーのキャリアインフラ「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。
現在データ連携が可能なSaaS:Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar
上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください: https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27
■ 株式会社overflowとは
株式会社overflowは、2017年6月 に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月 には「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。
● overflowに関する情報発信はこちら
・採用情報: https://jobs.overflow.co.jp/
・overflow Culture Deck: https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck
・podcast「overflow fm」: https://anchor.fm/overflowinc
・note「株式会社overflow Culture Note」: https://note.com/overflow_inc
● 株式会社overflow 会社概要
・会社名:株式会社overflow
・所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F
・代表取締役:鈴木 裕斗・田中 慎
・設立:2017年6月9日
・資本金:2億880万円
■「【2025年4月 版】各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度調査」のダウンロードはこちら
https://offers.jp/worker/wp/ai-coding-agent-survey-202504
■ 本調査結果データの引用について
本調査結果データを一部引用・二次利用等される場合は、「【2025年4月 版】各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度調査|Offers」と表記の上、リンクのご協力をお願いいたします。
リンク先: https://offers.jp/worker/wp/ai-coding-agent-survey-202504
【調査概要】
<調査目的>
各開発フェーズにおけるAIコーディングエージェント活用度調査
<調査方法>
Offersサービス会員に対して、サービス内でアンケートを実施
<調査期間>
2025年3月 上旬
<調査対象>
Offers会員ユーザー
<回答者数>
208名
※1|合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。
【調査目的とその背景】
2025年は「AIエージェントの年」と言われ、特にエンジニア界隈ではコーディングに特化したAIエージェントが大きな注目を集めています。しかし日本においては、海外と比較してジェネレーティブAIの活用率が依然として低く、企業での本格導入には信頼性・コスト・セキュリティ・企業文化など多くの障壁が存在していることが指摘されています。
「Offers」ではこれまで、プロダクト開発に関わる人材のマッチングを提供してまいりました。サービスを提供する中で、開発現場におけるAIツールの活用状況やその影響に関する情報が不足していることに気づき、より良いキャリア支援を行うためにも実態調査の必要性を感じました。
本調査では、現場で実際に活用されているAIツールや各開発フェーズごとの使い分け、導入メリットと課題を体系的に整理することで、「AIを使いこなす開発者」が活躍できる環境を整備するための貴重なデータを提供します。Offersとしては、急速に進化するAI技術の波に取り残されることなく、エンジニアの皆様に最適な支援を提供するため、現場の生の声を反映した情報発信を目指しています。
【調査結果】
<サマリコメント>
・AIコーディングエージェントは「日常的に使用」41.8%と「時々使用」21.6%で計63.4%が実際に活用中。
・GitHub Copilotが60.1%で圧倒的首位、Cursor(20.7%)の3倍のシェアを誇る。Claude Code(15.4%)、v0(14.9%)、Devinも10%以上で上位を形成し、Bolt.new(8.2%)、Windsurf(7.2%)が中堅層として続く。一強市場ながら特化型ツールも共存し、開発者は複数エージェントを状況に応じて使い分けている実態が見られる。
・AIコーディングエージェントの利用頻度は年代によって異なり、20〜40代は約6割が毎日または週に数回利用しているが、50代以上では利用頻度が低下し、未利用者(25.9%)も増加。
・AIコーディングエージェントはフロントエンド・バックエンド開発で最も活用され(50%以上)、デザイン・テスト分野も健闘(約33%)している。一方、要件定義・計画(25%)やデプロイメント・運用(10%未満)での採用は限定的。この傾向から、現在のAIツールがコード生成に強みを持つ一方、開発ライフサイクルの両端ではまだ発展の余地が大きいことがわかる。
・AIコーディングエージェント利用において「特にルールなし」が33%と最多であり、企業・個人双方での適切なガイドライン整備が今後の課題である。
<AIコーディングエージェント利用状況サマリ>
GitHub Copilotが60.1%で圧倒的首位、Cursor(20.7%)の3倍のシェアを誇る。Claude Code(15.4%)、v0(14.9%)、Devinも10%以上で上位を形成し、Bolt.new(8.2%)、Windsurf(7.2%)が中堅層として続く。一強市場ながら特化型ツールも共存し、開発者は複数エージェントを状況に応じて使い分けている実態が見られる。
<AIコーディングエージェントの利用経験の有無(年代別)>
全体として、若い世代ほど積極的にAIコーディングツールを活用する傾向が強く、年代が上がるにつれて「興味はあるが使用経験がない」層の割合が増加。ただし、どの年代においても「使ったことがないし、導入予定もない」という回答は少数派(10%前後)であり、AIコーディングツールの受容性は全体的に高いと言える。
<AIコーディングエージェントの利用経験の有無(経験年数別)>
経験年数3〜5年の開発者がAIコーディングを最も積極的に活用。日常的使用は全経験層で約40%と安定している一方、経験1〜3年の層には消極派が多く、5年以上のベテラン層では「使ったことがないが興味はある」が目立つ。
<AIコーディングエージェントの利用頻度(年代別)>
AIコーディングエージェントの利用頻度は年代によって異なり、20〜40代は約6割が毎日または週に数回利用しているが、50代以上では利用頻度が低下し、未利用者(25.9%)も増加。全体的に頻繁に使うグループと全く使わないグループの二極化が見られる。
<AIコーディングエージェントの利用頻度(経験年数別)>
経験3〜5年の開発者がAIコーディングツールを最も積極的に活用しており、約69%が週1回以上利用。「毎日」使用は全経験層で約35%と共通だが、経験1〜3年層では非利用者が30%と多く、5年以上層でも非利用者が約20%存在する。
<AIコーディングエージェント利用時のルール/ガイドラインについて>
AIコーディングエージェントの利用ルールは「特に定めていない」33.7%と「個人の自己ルール」29.3%で計63%が非公式な状態。一方、「企業ポリシーによる制限」26.4%を筆頭に約34%が組織的ルールに従い、「著作権規定」も1.9%ある。現状は個人判断が主流だが、情報保護の観点から公式ガイドラインへの移行が進みつつある様子がうかがえる。
<AIコーディングエージェントの利用歴について>
AIコーディングエージェントの利用歴は短く、3か月以内の新規ユーザーが31.3%と最多で、半年以内では半数近く(49.6%)を占める。1年以内の利用者は全体の71.7%に達し、2年以上のベテランはわずか7.7%にすぎない。この分布からは、AIコーディング支援ツールの普及が最近になって急速に進んでいることが読み取れる。
<AIコーディングエージェントの利用満足度>
AIコーディングエージェントへの満足度は高く、「満足」以上が59.3%で、特に「満足」が41.1%と最多。「どちらともいえない」も37.0%と多いが、否定的評価はわずか3.7%にとどまる。これはAIツールが広く受け入れられている一方、活用法の確立によってさらなる満足度向上の余地があることを表している。
<AIコーディングエージェントを利用している開発フェーズ>
AIコーディングエージェントはフロントエンド・バックエンド開発で最も活用され(50%以上)、デザイン・テスト分野も健闘(約33%)している。一方、要件定義・計画(25%)やデプロイメント・運用(10%未満)での採用は限定的。この傾向から、現在のAIツールがコード生成に強みを持つ一方、開発ライフサイクルの両端ではまだ発展の余地が大きいことがわかる。
【直近開催予定のイベントご案内 #Offers_DeepDive】
① 多要素認証じゃダメ?ritouさん、Auth屋さんに聞く 認証技術の最前線 ~パスワードレスとは~
<イベントでわかること>
・パスワードレス認証とは?
・各認証技術(パスワード認証、二段階認証・多要素認証、パスワードレス認証)の成り立ち
・認証技術を検討する際の技術選定のポイント
<開催概要>
・【開催形式】オンライン開催
・【日時】2025年4月17日(木) 19:00~20:00
■本イベント参加申し込み・詳細はこちら
https://offers.jp/worker/events/connpass_56
② そのID管理、サービス増えても大丈夫? LayerX/kubellに聞く 後から後悔しないID基盤設計
<イベントでわかること>
・実際のマルチプロダクト移行事例、直面した課題
・マルチプロダクトを考えるにあたり意識すべきID管理設計
・IDaaSとの向き合い方
<開催概要>
・【開催形式】オンライン開催
・【日時】2025年4月23日(水) 19:00~20:00
■本イベント参加申し込み・詳細はこちら
https://offers.jp/worker/events/connpass_57
Offersでは、本調査以外にも最新の技術トレンドやエンジニアのキャリアに関する様々な情報を発信しています。ぜひご覧ください。見逃し無料配信!続々追加中!
︎過去の人気イベントのアーカイブ配信はこちら
https://offers.jp/worker/events
■ 「Offers(オファーズ)」とは
「Offers」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月 に正式リリースし、2024年4月 時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。
● Offersに関する情報はこちら
・「働くを楽しく」するマガジン「Offers Magazine」: https://offers.jp/media
・開発組織におけるHR担当者やマネージャーのための情報メディア「Offers HR Magazine」: https://hr-media.offers.jp/
・副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」: https://offers.jp/jobs
・プロダクト開発の知見が集まるQ&Aプラットフォーム「Offers Q&A」: https://offers.jp/qa
・デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」: https://hr-lab.offers.jp/
■ 「Offers MGR(オファーズマネージャー)」とは
「Offers MGR」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、エンジニア、PM、デザイナーのキャリアインフラ「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。
現在データ連携が可能なSaaS:Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar
上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください: https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27
■ 株式会社overflowとは
株式会社overflowは、2017年6月 に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月 には「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。
● overflowに関する情報発信はこちら
・採用情報: https://jobs.overflow.co.jp/
・overflow Culture Deck: https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck
・podcast「overflow fm」: https://anchor.fm/overflowinc
・note「株式会社overflow Culture Note」: https://note.com/overflow_inc
● 株式会社overflow 会社概要
・会社名:株式会社overflow
・所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F
・代表取締役:鈴木 裕斗・田中 慎
・設立:2017年6月9日
・資本金:2億880万円



